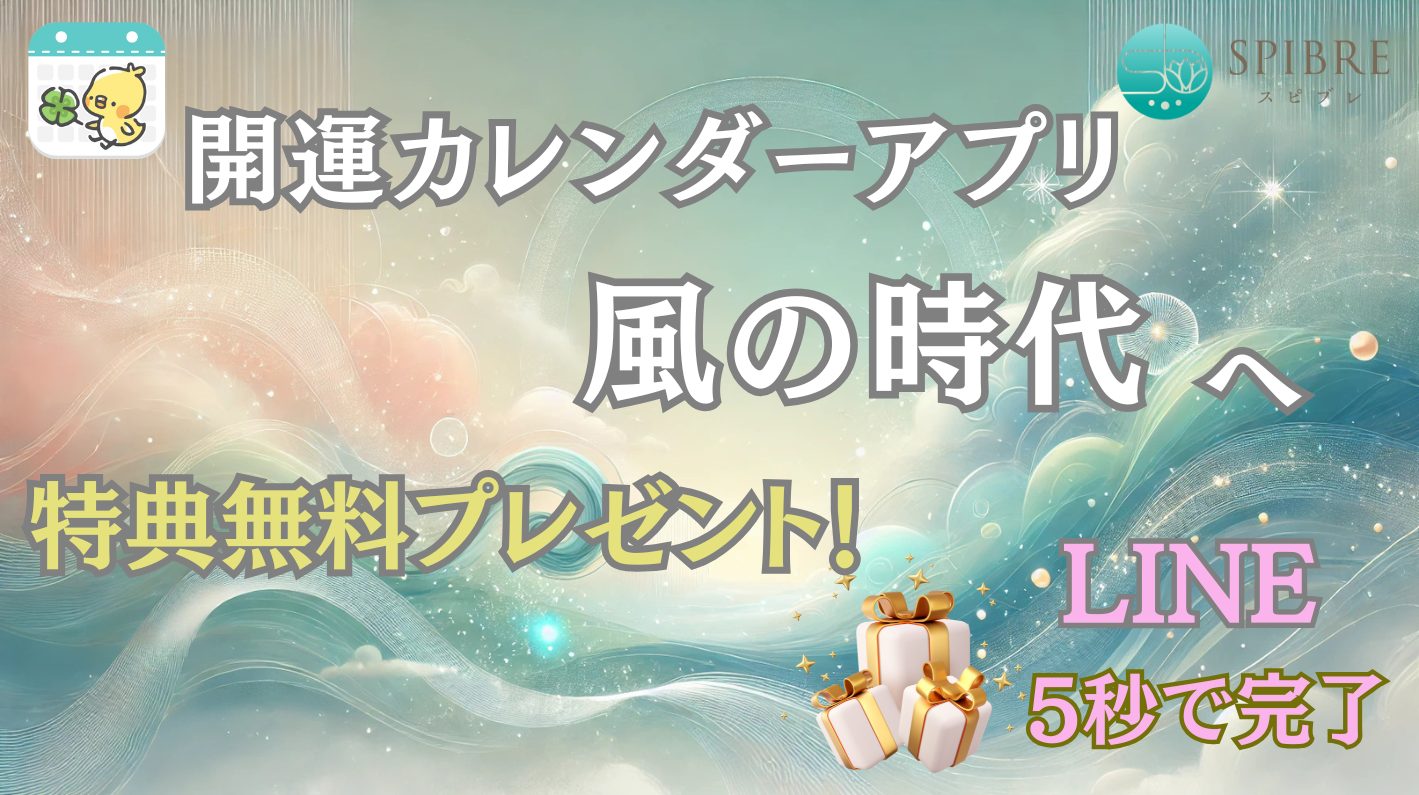大阪市内の便利な場所に位置し、地元の人々にとっては古くから通称「あびこ観音」と呼ばれて親しまれてきたこのお寺は、特に節分に開催される「厄除け」の護摩焚きの儀式に、全国からの多くの人で賑わいます。
街の真ん中の喧騒の中に、突然現れる閑静なエリアに佇む「あびこ観音」は、なんと日本最古の観音菩薩の霊場であり、従って日本最古の観音寺でもあるのです。
では「厄除け」の寺院としても有名なこの「あびこ観音」の歴史やご利益などには、どのようなものがあるのでしょうか?
目次
日本最古の観音寺『あびこ観音』の起源

Photo by S.Hosaka
通称「あびこ観音」の正式な呼び名は『吾彦山 大聖観音寺』で、大阪市住吉区に位置しています。
ここは日本最古の観音寺で、観音宗総本山の寺院なのです。
「吾彦山」というのは、この地方の豪族であった『依網吾彦(よさみのあびこ)』が起源となっています。
「あびこ観音」の歴史は、もともとはこの地方の豪族『依網吾彦』の一族が百済と貿易をしていたときに、百済の聖明王から、身の丈一寸八分(約5.5cm)の観音像を贈られ、欽明天皇時代の546年に、その像を祀るための寺を創建しました。
そのあと、聖徳太子がこの地を訪れたときに、観音菩薩のお告げを受けられ、607年にその観音像を祀るための立派な観音寺を、この地に建てられたと伝えられています。
また1615年の大阪の夏の陣の時には、真田信繁に攻められて逃げてきた徳川家康をここに匿って、命を救ったことでも知られています。
「あびこ観音」の最盛期は江戸時代で、その頃には境内になんと36もの支院(本寺の境内内に存在し、本寺に付属する小寺院)がありました。
しかし1881年(明治14年)の火事で多くが焼失し、その後1890年(明治23年)に再建されました。
その後「あびこ観音」は、毎年2月3日に「節分厄除大法会」を開催するようになり、「厄除け」のための盛大な護摩加持祈祷が行われ、ご本尊が開帳されるので、日本全国から多くの人が訪れることで有名です。
●「あびこ観音」所在地:大阪市住吉区我孫子4丁目1-20
「あびこ観音」の護摩焚き祈祷、ご利益

「あびこ観音」においてもっとも大きな行事が、節分に開催される「節分厄除大法会」で、毎年2月1日から7日の間(年によって多少日程に違いあり)、「厄除け」の護摩加持祈祷が盛大に行われます。
この期間中は、護摩堂にて護摩堂本尊の「不動明王」に『聖観音像』のご本尊の前で祈祷し、修験行者が護摩木を、昼夜を問わずお焚き上げをしています。
この護摩堂のご本尊である「不動明王」は、921年に醍醐天皇の皇后がご懐妊されたときに安産祈願の祈りを込めて贈られたもので、毎年特にこの節分祭の間は威力を発揮して、様々な願いを叶えてくれるとされています。
このお寺のお焚き上げ方式は「天蓋護摩」方式と呼ばれ、天蓋と呼ばれる重ね貼り合わせた特製の奉書紙の中に霊符を入れ、それを護摩炉の上に吊るします。
そしてなぜかこの天蓋は、護摩炉の炎が近くに至っても燃えないのだそうです。
炎の中にくべられた、願い事が書かれた護摩木が燃え上がる様子は、かなり近くで見ることができ、その炎の迫力からなんとも不思議なパワーを得られるような感じがあります。
なんでもその炎には不動明王のパワーが宿っていると考えられているのです。
このとても神秘的な行事においては、「厄除け」以外にも、「所願成就」「開運」「交通安全」「安産祈願」などもお祈りすることができます。
この特別行事である「節分厄除大法会」の日以外でも、「あびこ観音」にお参りすることで、「厄除け」「開運」「諸願成就」「身体健勝」「交通安全」などのご利益を得ることができるので、ぜひ一度立ち寄ってみましょう。
「あびこ観音」境内にある楠の大木パワー

「あびこ観音」の山門を入ったところにあるのが、樹齢800年の大きな楠です。
その高さは19.5メートル、周囲は4.8メートルもある立派な大木です。
この木は室町時代から、大阪夏の陣をはじめ、日清・日露戦争及び太平洋戦争と、幾度の戦火も潜り抜けて生き残った楠で、大阪市の保存樹にもなっており、「観自在楠」と命名されています。
「観自在」というのは仏教用語で、「すべての事物を自由自在に見ることができる」という意味なのです。
800年の歴史をずっと見守ってきたと同時に、私たちをお見守りくださいという意味で名付けられているそうです。
この木のそばに立つだけでも、何かすがすがしさと壮大なパワーを感じ、力を得ることができる、パワースポットなのです。
白龍池の錦鯉たち

Photo by S.Hosaka
「あびこ観音」の「金辰殿」という、白竜弁財天をお祀りし、商売繁盛のご利益があるお堂の横にあるのが「白龍池」です。
平成30年10月に作られた比較的新しい石造りの池ですが、池の側面はガラス張りになっているので、池の横からも錦鯉を楽しむことができるようになっています。
これらの立派な錦鯉の中には、1メートル近い大きなものもあり、また「ザック」と呼ばれている赤い模様が美しい鯉は、関西地区の錦鯉品評会で優勝もしています。
この池にはたくさんの錦鯉が泳いでいますが、その中でも真っ白な鯉がいます。
実はこの鯉は、この池の主なのですが、時々池の側面のガラスのところから見ていると、自分のほうに向かって泳いできてくれたりします。
この白い鯉に出会えたら、幸運になるという話もあり、一度ぜひ試してみてください。
「あびこ観音」を満喫しよう

「あびこ観音」には、このほかにもご利益を授かれることが色々とあります。
「びんずるさん」のご利益
「あびこ観音」に鎮座する「びんずるさん」と呼ばれる仏像があります。
「びんずるさん」は別名「羅漢(らかん)」さんで、なんでも最高位の修業をした聖者なのだそうです。
釈迦の弟子のうち最高位の人であり、超能力を有し病気を治す力を持っていたとされています。
そんなことから、「びんずるさん」の像で自分の身体の悪い部分と同じ個所をなでることで、病気が治癒するとされています。
御朱印
「あびこ観音」の御朱印には2種類あり、ひとつは「観世音」、もうひとつは「円通殿」と書かれています。
「観世音」がご本尊の「聖観世音菩薩」を意味し、もうひとつは本堂の別称なので、通常は「観世音」のほうを求める人が多いようです。
とても美しい文字で丁寧に書かれたこの御朱印からは、非常にすがすがしさや神々しさを感じてしまいます。
「あびこ観音厄除け饅頭」
「あびこ観音」前にあるお饅頭屋さんで売っているのが「あびこ観音厄除け饅頭」です。
この饅頭はとても有名で、「元祖厄除け饅頭」と呼ばれています。
黒糖使用の蒸し饅頭ですが、厄除け祈願のお土産として喜ばれるため、いつも早めの時間で売り切れているようです。
「あびこ観音」にお参りしたら、忘れずにこの厄除け饅頭を買って帰るのが、お参りの常連さんにとっては厄除け詣での完了となるのです。
まとめ
大阪市内の街中にありながら、日本最古の観音寺である「あびこ観音」は、厄除けで有名です。特に節分の時に催される護摩焚き行事には全国から人々が訪ねてきて、盛大に開催されています。