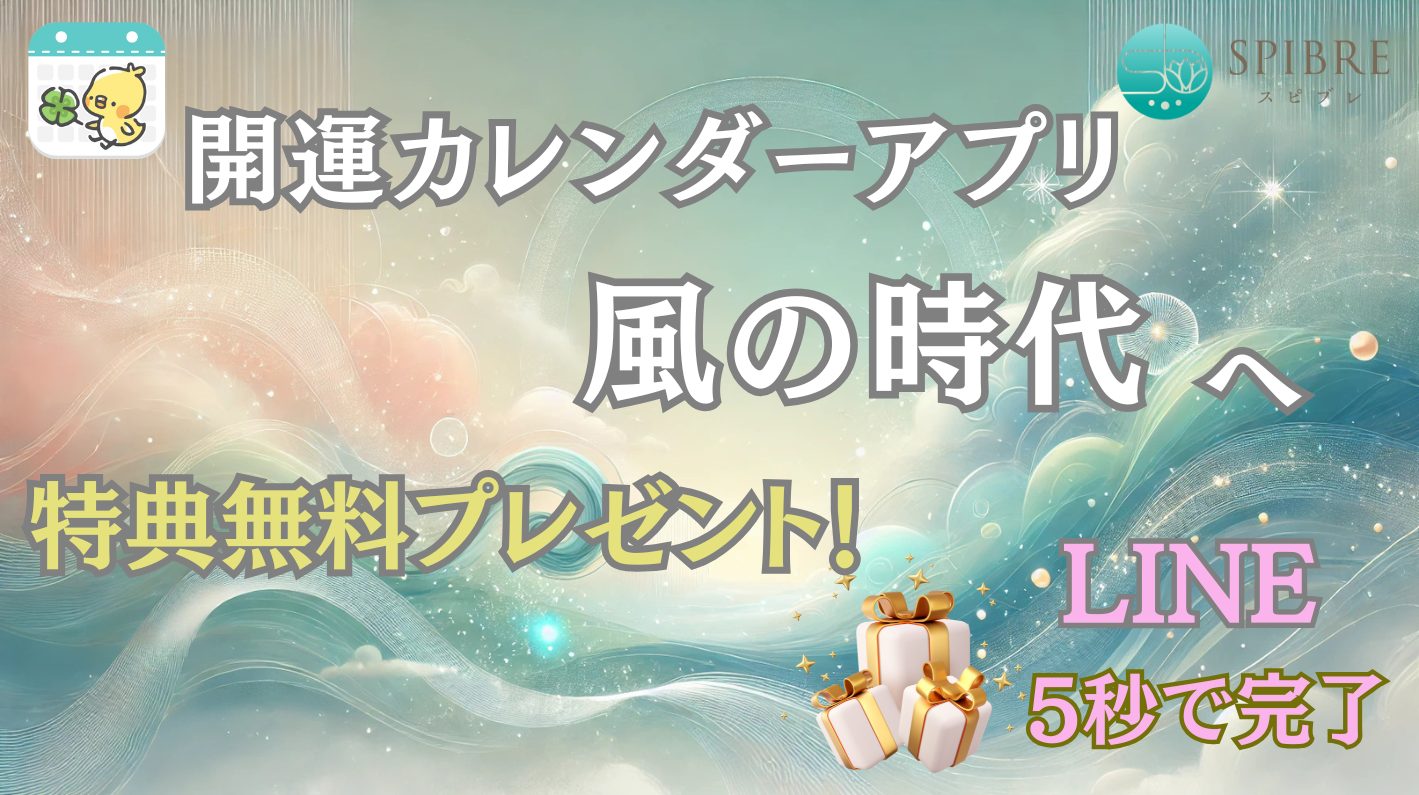初詣以外でも、観光やお参りのために寺社仏閣を参拝されることがあると思います。
最近では参拝するだけではなく、御朱印という、それぞれの寺社において筆文字に朱印を押していただくものを集める方も増えています。
では御朱印にはいったいどのような楽しみ方があるでしょうか?
御朱印で運気をアップする5つのマナーや秘訣
それぞれの寺社を訪れると、禰宜や僧侶が丁寧に筆で一文字ずつ寺社の名前などを書き、朱印を押した御朱印をいただくことができます。参拝のマナーを正しく守りながら、この御朱印を有り難くいただくことで運気を呼び寄せることも可能なのです。
御朱印とは
御朱印のルーツは、西国三十三ヵ所観音霊場や四国八十八か所霊場などの霊場巡りの際に、廻った場所の証としてや、写経を収めた証としていただけるものでしたが、そのうち観光で訪れる人のために、参拝の証としていただけるようになりました。
よって御朱印をいただけるのは寺では「納経所」である場合が多いようです。寺社によってそれぞれ御朱印のスタイルがあり、最近では御朱印をいただく御朱印帳も様々なデザインのものが売られるようになり、神社用、寺用とそれぞれ分けて朱印帳を持ち歩く人たちも多くなりました。
御朱印の楽しみ方
御朱印は濃い墨を用いて独特の筆使いで描かれ、その上に朱印を押していただくものです。
書いてくださる方によってその字体や雰囲気も様々で、朱印もいろいろなデザインのものがあります。ときには期間限定の御朱印もあり、たまたまその時期に寺社を訪れることができれば、幸運と考えてよいでしょう。
また朱印帳も各寺社で、その寺社を象徴するようないろいろなデザインのものが発売されているほか、最近では雑貨店などでもユニークなデザインのものが多くでまわっているので、自分の好みに合ったものを探し求めると、楽しさもアップします。
いただくときのマナー
御朱印をいただくときに守りたい、いくつかのマナーがあります。
御朱印を押していただくのはメモ帳やノートではなく、御朱印帳を使います。また寺社を訪れてただちに御朱印をいただきに行くのでは、礼儀知らずになります。スタンプラリーを楽しんでいるのではないので、神々が住まわれる神聖な場所において、まず正しく参拝することです。
神社であれば鳥居を、寺であれば正門をくぐる前に一礼をし、神様の通り道とされる参道の真ん中は避けて端を歩くのがマナーです。
それから手水屋で左手、右手、口の順で清めます。本殿の前でお賽銭を入れ、神社であれば2拝、2拍手、1礼をして拝みます。それから御朱印をいただきに行くのがマナーです。
御朱印は300円程度の料金を支払っていただきます。できるだけお釣りがいらないようにお支払いします。受け取るときは、両手で感謝の気持ちを込めて受け取るようにしましょう。
御朱印の保管先
御朱印は、神様や仏様と同じように大切なものです。決して粗末には扱わないようにしましょう。バッグの中に入れっぱなしにしたりしないことです。
常に浄化された場所、仏壇や神棚に置いておくのがベストですが、なければきれいに整理整頓された本棚の中や引き出しにしまっておいてもかまいません。
ただしほかの雑貨などと一緒にしまいこまず、御朱印帳だけの場所を確保するようにしてください。そうすることによって、御朱印帳があなたのお守りのような存在になってくれるのです。
御利益のある御朱印
御朱印を集めるときに、行きあたりばったりで寺社に行くのでは、御利益もあまり期待できないかもしれません。それよりも自分の願いに合った場所に出かけていただくほうが運気アップにつながります。
関東では、
「伊豆美神社」「五条天神社」「今戸神社」
関西では、
「平安神宮」「伊弉諾(いざなぎ)神宮」「八坂神社」
関東では、
「江島神社」「深川不動堂」「銭洗弁財天宇賀福神社」
関西では
「伏見稲荷大社」「西宮神社」「車折神社」
関東では、
「愛宕神社」「鶴岡八幡宮」「成田山新勝寺」
関西では、
「日吉大社」「大神神社」「応頂山勝尾寺」
まとめ
いかがだったでしょうか?
最近とても人気の高い御朱印集めですが、それぞれの寺社の歴史や背景を知ったり、印の意味を読み説いたりすることによって、御朱印のありがたさが増すことでしょう。
寺社仏閣参拝の正しいマナーを守りながら、楽しんで御利益を授けていただけるように集めてみるとよいでしょう。
▶︎あらゆる開運方法で幸運を呼び込む体質になる!まとめ一覧ページはこちら