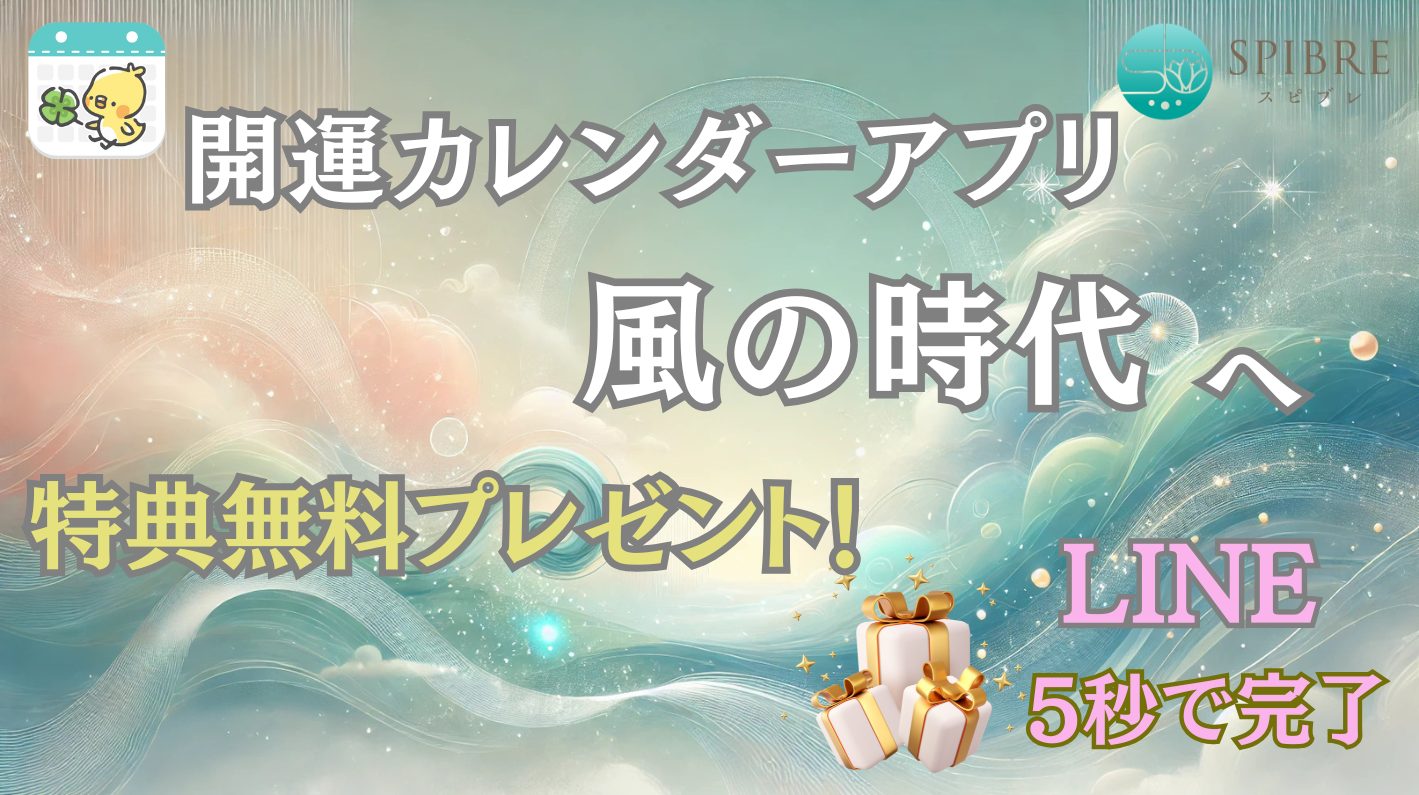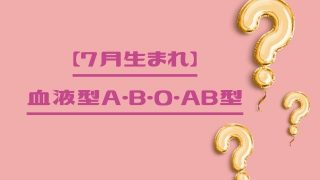秋の七草のひとつである「ハギ(萩)」は、古くから日本では親しまれてきた花です。
「ハギ」は、万葉集の中でも多く詠まれている植物のひとつであり、お月見には必ずといってよいほどススキと共に飾られる、風情のある花を咲かせます。
では日本や東アジアや北アメリカが原産の「ハギ」が持つ、スピリチュアル的な意味やエピソードなどには、どのようなものがあるのでしょうか?
目次
【ハギ】にまつわるスピリチュアルなお話

「ハギ」にまつわる日本の逸話①
出羽の国の郡司であった小野良真には3人の子供がいましたが、末っ子だけは後妻との間に生まれた子供でした。
良真が出かけたある日、その後妻は屋敷内の池に「ハギ」の枝を使って橋を作り、先妻の子供たちにその橋を渡るように命じ、ふたりを池で溺れさせてしまったのです。
良真が戻ると子供たちが見当たらないので探してみると、どこからか白い鳥が飛んできて「ハギの橋を渡るとてザンブラのコブラ」と鳴いたのです。
まさか…と思いつつも良真は後妻を問いただして、子供たちを死なせたことを白状させたものの、亡くなった子供たちは戻ってきません。
良真は後妻を離縁し、残った末娘を大切に育てたのでした。
そしてこの末娘こそが、あの小野小町になったと伝えられています。
「ハギ」にまつわる日本の逸話②
大萩という集落で、お寺の工事があり、日本国中からいろいろな名木が集められました。
そしてこの集落にあった「ハギ」の大木も、お寺の改修工事に使うために切り倒されたのですが、どちらが根でどちらが木の先なのかわからなくなってしまいました。
困り果てた役人は、これを見分けることができたものには褒美をやることにしたのです。
するとひとりの若者が、その「ハギ」の木を川に入れ、浮いたほうが木の先端で、沈んだほうが木の根っこのほうだと見分けたのです。
役人が「褒美には何が欲しいか?」と聞いたところ、若者は「この「ハギ」の木の見分け方は、私の親より教わったことです。親は今年62歳になり捨老の制によって野に親をすてなくてはならない年齢ですが、それはあまりにもかわいそうで、秘かに隠してきました。どうか今日の褒美として、親が長く生きられるようにしてください」と頼んだのです。
これがきっかけとなって、その捨老の制は廃止され、若者は最高の親孝行をしたのでした。
【ハギ】が誕生花の日
【ハギ】が誕生花です。
- 9月5日
- 9月6日
- 9月13日
- 9月18日
- 9月24日
- 9月25日
- 10月1日
- 10月15日
- 11月15日
【ハギ】を使って運気をアップする方
ここで説明する風水は、「誰でもできるかんたん風水!バグア・チャート風水」
伊庭野れい子著(太玄社)
著者ご本人に解説してもらいます。
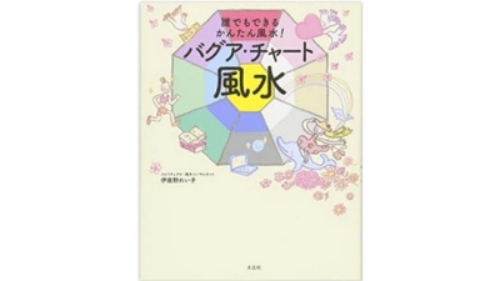
(本の解説)
ハワイ在住の風水師クリア・イングレバート氏(『ハワイアン風水』著者)に師事した著者が、バグア・チャートを使った風水を基本からよりわかりやすく、誰でも手軽に自宅で実践できるようにイラスト付きで解説した開運風水本。

風水で運気UP
「ハギ」は、風水では縁起がよい木とされ、庭木として白色の「ハギ」を北西に植えます。
「ハギ」は成長が早く、エネルギーを活性化してくれるため、繁栄や富を引き寄せる木と考えられています。
またエネルギーのバランスも取るので、エネルギーが乱れているように感じる部屋や玄関などに生けておくのも効果的です。
花言葉【ハギ】の意味
「ハギ」は、東アジアや北アメリカが原産で、草花のように思う人も多いかもしれませんが、実は落葉低木です。
日本では古くから万葉集にも詠まれ、秋の花として知られていますが、実は真夏頃から咲き始めます。
日本では主に山野に自生していますが、庭木などにも用いられることが多い植物です。
「ハギ」はマメ科の植物なので、その花もほかのマメ科の花のように小さな蝶々のような形をしています。
そして枝垂れた細い枝にたくさんの花を付けるのも特徴です。
「ハギ」は漢字で書くと「萩」で、秋の草花と考えられているため、秋の上に草冠がついたとされています。
またその名前の由来は、古い株の根もとあたりから、新芽が出るために、「生え木」がいつしか「ハギ」に変化したとされています。
「ハギ」は、秋の七草とされていますが、実は「ハギ」には婦人病に効果のある成分が含まれており、中国では乾燥させてお茶として飲み、また日本でも若芽を天ぷらやおひたしにします。
「ハギ」には白、ピンク、紫、赤紫などがありますが、色別の花言葉はありません。
「ハギ」の花言葉①
- 柔軟な精神
この花言葉は、「ハギ」は茎が柔らかく、枝も細くてしなるため、そこからこの花言葉が付けられています。
「ハギ」の花言葉②
- 内気
- 思案
これらの花言葉は、「ハギ」が枝垂れた枝に花を咲かせ、下を向いてはずかしそうにしている様子であったり、何か思案をしてうつむきかげんであるように見えることから付けられています。
「ハギ」の花言葉③
- 親孝行
この花言葉は、「ハギ」にまつわる逸話から付けられており、「ハギ」の木の先端と根を見分けた若者に対して、役人がその褒美を尋ねたときに、自分の親が長く生きられるように、それまであった捨老の制を廃止させたということに基づいています。
「ハギ」の花言葉④
- 残酷
この花言葉も「ハギ」の逸話から付けられており、継母が自分の子供でなかったふたりの子供を溺死させ、自分の子供だけ生かしておいたという話に基づいています。
「ハギ」の花言葉⑤
- 優美
- 風雅
これらの花言葉は「ハギ」の花が万葉集でよく詠まれていることから、貴族の生活を垣間見るようで、付けられた花言葉です。
花言葉【ハギ】の基本情報
| 科 属 | マメ科 ハギ属 |
| 原産地 | 東アジア、北アメリカなど |
| 品種 | 約60種 |
| 開花時期 | 7月~10月 |
| 英語和名 | ・Bush Clover(ブッシュ・クローバー) ・ハギ(萩)、ヤマハギ、胡枝花(こしか)、庭見草(にわみぐさ)、野守草(のもりぐさ)、初見草(はつみぐさ)、風草(かぜぐさ)、秋知草(あきしりぐさ)、秋遅花(あきちはな) |
まとめ
「ハギ」は、古くから万葉集にも好んで読まれ、風情のある花として親しまれてきました。その花言葉は、枝垂れた枝に上品に咲く、そんな花姿にちなんだものが多く、また逸話に基づいたものも用いられています。