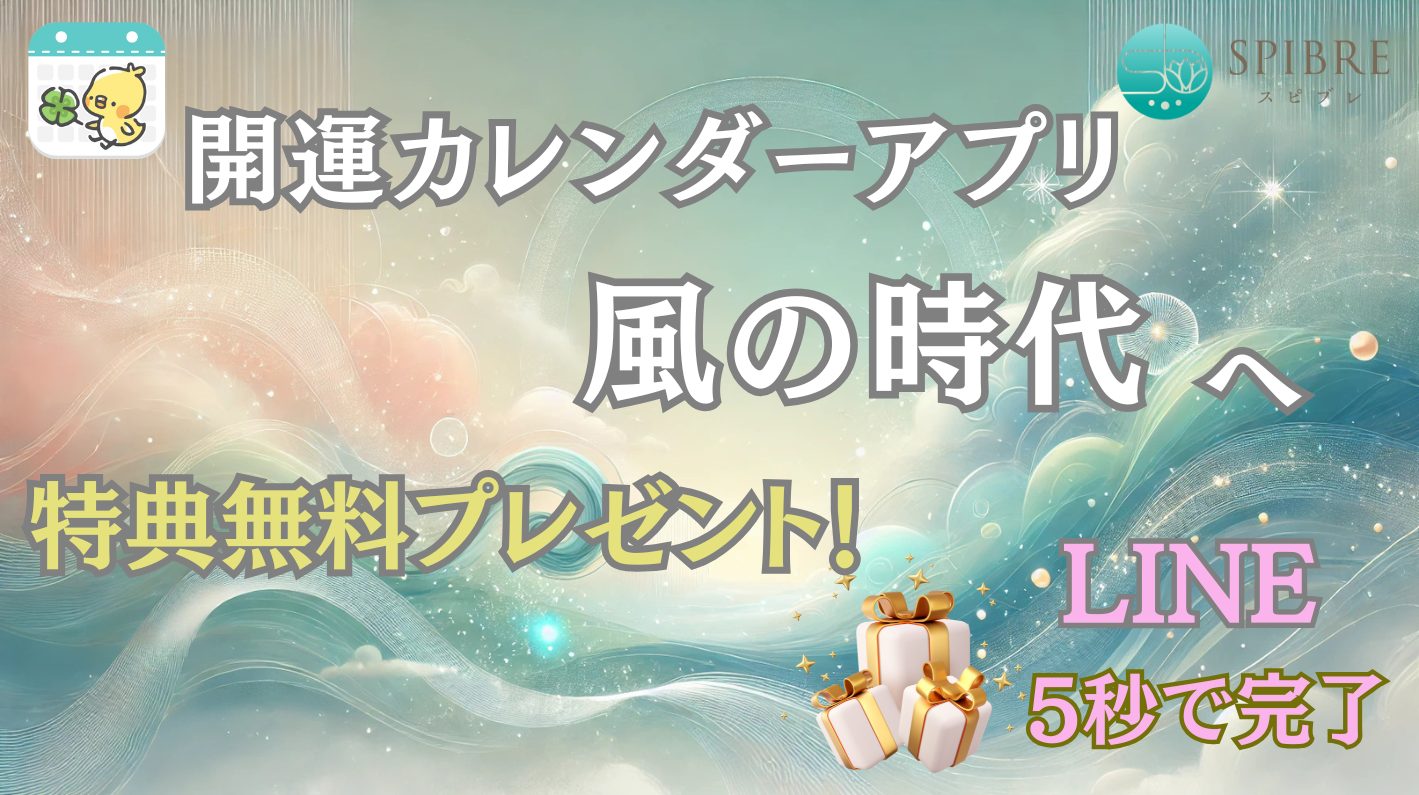春と言えば、花見。咲き誇る桜の美しさは、日本でしか見られない毎年の風物詩です。日本人に古くから愛されてきた花ですから、日本には桜に関することわざが数多く存在します。桜の春を感じるような心に響くメッセージを読んでみてはいかがでしょう。
今回は、桜に関することわざ一覧をご紹介します。ことわざに詳しいと、花見の際に周囲の人から一目置かれるかもしれませんよ。
桜のことわざ
日本の国花でもある桜。日本には、そんな桜の美しさに影響されて生まれた言葉がたくさんあります。桜は咲いてから散るまでが非常に短く、儚さや無常さを感じさせる花。日本人独特の「侘び寂び」文化にも強い影響を与えています。
次の項からは、そんな桜に関することわざを一覧でご紹介します。詳しい意味や由来も解説しますから、最後まで目を通してみてください。春を感じるメッセージが、あなたの心に響いてくるかもしれません。
明日ありと思う心の仇桜
明日ありと思う心の仇桜は、桜がいかに儚い存在であるかを喩えた言葉です。
美しく咲いている花が明日も見ることができるだろうと考えていると、見ることができないまま散ってしまうかもしれないという意味のことわざです。世の無常さを表現する言葉であると同時に、せっかくの機会を損失することがないようにしようという意味を持っています。
三日見ぬ間の桜
三日見ぬ間の桜は、桜の花が非常に短命であることを指す言葉です。
桜の花は三日で散ってしまうほど儚いものであるということわざです。また、世の中の移り変わりが激しいことを喩えた世の中は三日見ぬ間の桜かなという言葉もあります。花の儚さや無常さだけでなく、世の中の無常さをも意味することわざであると言えるでしょう。
酒なくて何の己が桜かな
お酒がなければ花見も月見もまったく面白くないという意味のことわざです。
花見にはお酒がつきものであるという意味でもあります。また、似たような言葉に花より団子ということわざがありますが、これは花見よりも食べ物に夢中になることを指す言葉で、酒なくて何の己が桜かなはあくまで花見を無視してお酒に夢中になるという意味ではありません。
花は桜木人は武士
花は桜木人は武士は、人の美しい生き方に関することわざです。
花の中でもっとも良いのがパッと咲いてすぐに散る桜であるように、人間も美しく咲いて潔く散る武士がもっとも良い生き方であるとする言葉です。日本独自の武士道を感じさせることわざですね。また、もっとも優れた花は桜であり、もっとも優れた人が武士であるという意味もあります。
桜切る馬鹿梅切らぬ馬鹿
桜切る馬鹿梅切らぬ馬鹿は、桜と梅といった庭木の剪定をいう言葉です。
梅は古い枝はどんどん悪くなってしまうので剪定の必要があります。一方で、桜は切ると切り口から腐ってしまうので剪定することは厳禁です。そんな桜と梅の剪定方法を指すことわざですが、その人の個性に合った育て方をしたほうが良いという意味も持っています。
桜は花にあらわる
花が咲いてはじめてそれが桜の木であったことを知るという意味のことわざです。
桜の木は特徴があまりなく、これまで何の木とも知ることができなかったのが、春に桜の花が咲いたのを見てやっとその木が桜の木であったことを知るという様を喩える言葉です。また、それまでとは普通であっても、才能ある人は機会を得ると途端に才能を発揮することができるということも意味します。
桜は七日
桜の花の寿命は、わずか七日ほどであることを意味することわざです。
桜はすぐに散ってしまうため、儚さを感じさせる花です。このことわざは、桜を見に行くときには開花してから七日以内に行ったほうが良いということも意味します。また、そんな桜の寿命から転じて盛りの時期が短いことの喩えとしても用いられることもあります。
桜三月菖蒲は五月
桜三月菖蒲は五月は、時季の花をいった言葉です。
このことわざは、桜の花は三月が花盛りになるが、菖蒲の花は五月が見頃になることを指しています。季節によって美しい花が変わることを意味しています。また、桜や菖蒲を見たいと考えたときにパッと見事の時期が思い出せるので、便利なことわざと言えるでしょう。
桜流し
桜流しは、散った桜が水に流れる様を指す言葉です。
日本各地で使われているこの言葉ですが、実は鹿児島地方の方言なのだそうです。また、散った桜が水に流れる様を指すだけでなく、桜が開花する時期に降る長雨の意味も持っています。雨が降ることで桜を散らしてしまいますから、桜の持つ儚さを表現しています。
まとめ
日本には、その季節の花や風景を愛でるという文化があります。桜は、そんな季節の花の中でもっとも日本人に愛されてきた花と言っても差し支えありません。桜を見るときには、そんな桜に思いを馳せてみてはいかがでしょう。
▶︎【桜のスピリチュアル】神様やエネルギー・花びら・季節外れはこちら