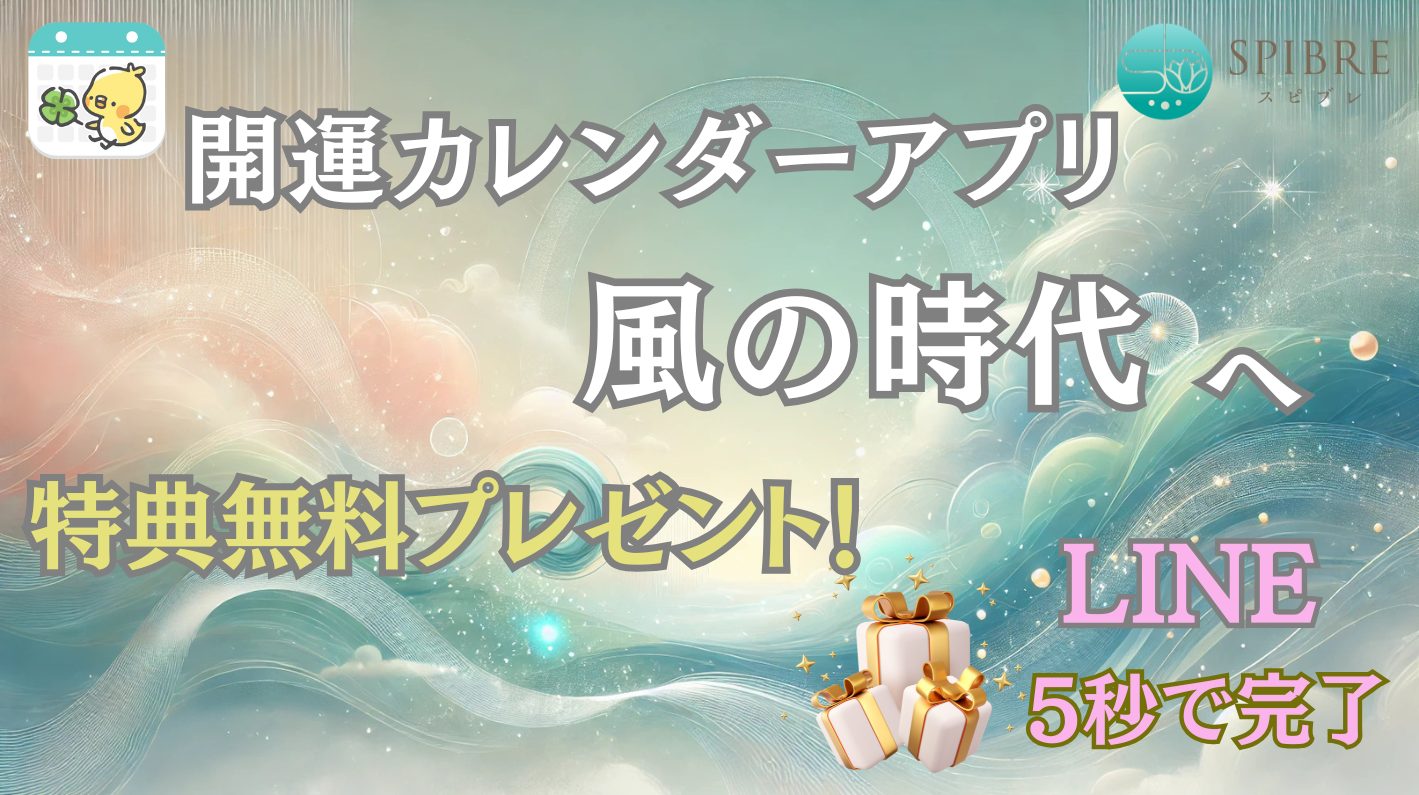淡く優しいピンク色や、早春を思わせるような薄い緑色。見ているだけでも気持ちがふんわりと癒されるような「草木染」の作品を、みなさんも手に取ったことがあることと思います。
草木染は自然に生える植物から抽出した天然の染料を用いて、糸や布を染めたもので、その原料となる素材も世界中に多く存在しています。
化学染料とは違い地球に優しいというだけでなく、身体にも優しいという草木染には、どのような効能やスピリチュアル的な意味があるのでしょうか?
草木染の歴史

「草木染」は、実は世界各地に古くから存在する染色方法です。
中国やヨーロッパでは、紀元前には草木染が始められており、日本でもなんと縄文時代には、すでに草木染が行われていたというのです。
日本で現存する最古の草木染は、佐賀県にある吉野ヶ里遺跡から出土した絹織物に使われていた草木染の染料で、これが弥生中期のものであろうと言われています。
また万葉集にも草木染のことが詠まれていたり、聖徳太子の時代になると、その冠位十二階制度の冠位を草木染の色を用いて表し、最上位を表す高貴な色の紫には、「紫根」を用いていました。
そして平安時代以降は、美しい草木染の色彩が着物に取り入れられてゆくようになり、染色技術も向上してきました。
江戸時代になると、庶民でも身に着ける木綿の布地を藍色に染める「藍染」が、流行し始めました。
しかし明治時代に入ると、合成染料が海外から持ち込まれ、これによって草木染は残念ながら急激に衰退していったのでした。
ところが最近では、その自然の色の美しさや、環境にも優しい草木染が、再び脚光を浴びつつあるのです。
草木染の特徴

草木染は、平安時代の頃にはすでに100種類以上の色があったとされています。
天然の草木などを使って染めるため、行く通りにも色を作ることができ、同じ草花でも摘果する時期によって色が異なってきます。
また同じ草木を使ったとしても、その出来上がりは均一ではなく、微妙な違いが出てくるのです。
そして年月が経つと、その色合いは当然ながら色々な条件によって変化してくるため、最初に染めた色とは違った色を楽しめるというメリットもあるのです。
それがかえって草木染の特徴となり、化学染料では出せないような優しい風合いをかもしだすことができるわけです。
驚いたことには、昔の人々は草木染の色が美しいから身に着けていただけではなく、その草花が持つ薬効や、スピリチュアル的な効果も知った上で身に着けていたのです。
また天然の素材を用いることで、人と環境にも優しく、まさに今のSDGsの時代にピッタリとくる染色技法でもあります。
草木染の海外におけるスピリチュアル的な使用法

海外においても草木染は、最近色々な意味で注目を浴び始めています。
海外の人々にとって、天然の草木を用いて染めるということは、自然との調和を図ることを意味しています。
そしてその植物が育った土地との直接的で神秘的な繋がりすらも感じることができるので、草木染はまさにスピリチュアルな染色であると考えています。
また土地との直接的なつながりを呼び起こす古代の芸術でもある草木染は、抽出された色がどれも温かさとエネルギーに満ちているのです。
天然の植物を用いた染色は、植物への畏敬の念を持って取り組むことで、ざらにスピリチュアルな体験を生むことができます。
その染色プロセスには、火、水、土などの要素が組み合わされており(つまり、火を使ったり、水を混ぜたり、土を使ったりして染め上げるため)、まさに自然との融合であり、錬金術的な体験でもあります。
また世界各国で、草木染の意味は色々と違ってきます。
たとえば西アフリカにおいて、藍染は非常にスピリチュアル的な意味が深く、藍の植物自体が「神様の木」として知られているのです。
インドにおいては、天然の色彩が人間の精神と深いつながりがあるとされ、桑やターメリック、ハリタキ(生薬の一種)、マンジスタ(ハーブの根から抽出される液)などを用いて古くから布を染めていました。
実はこれらの染料は、アーユルヴェーダ医学でも、治療や癒しの効果があるものとして用いられてきたのです。
そして天然の草木で染め上げた布を身に着けることで、自然と調和し、また癒しの効果も得られると考えられているのです。