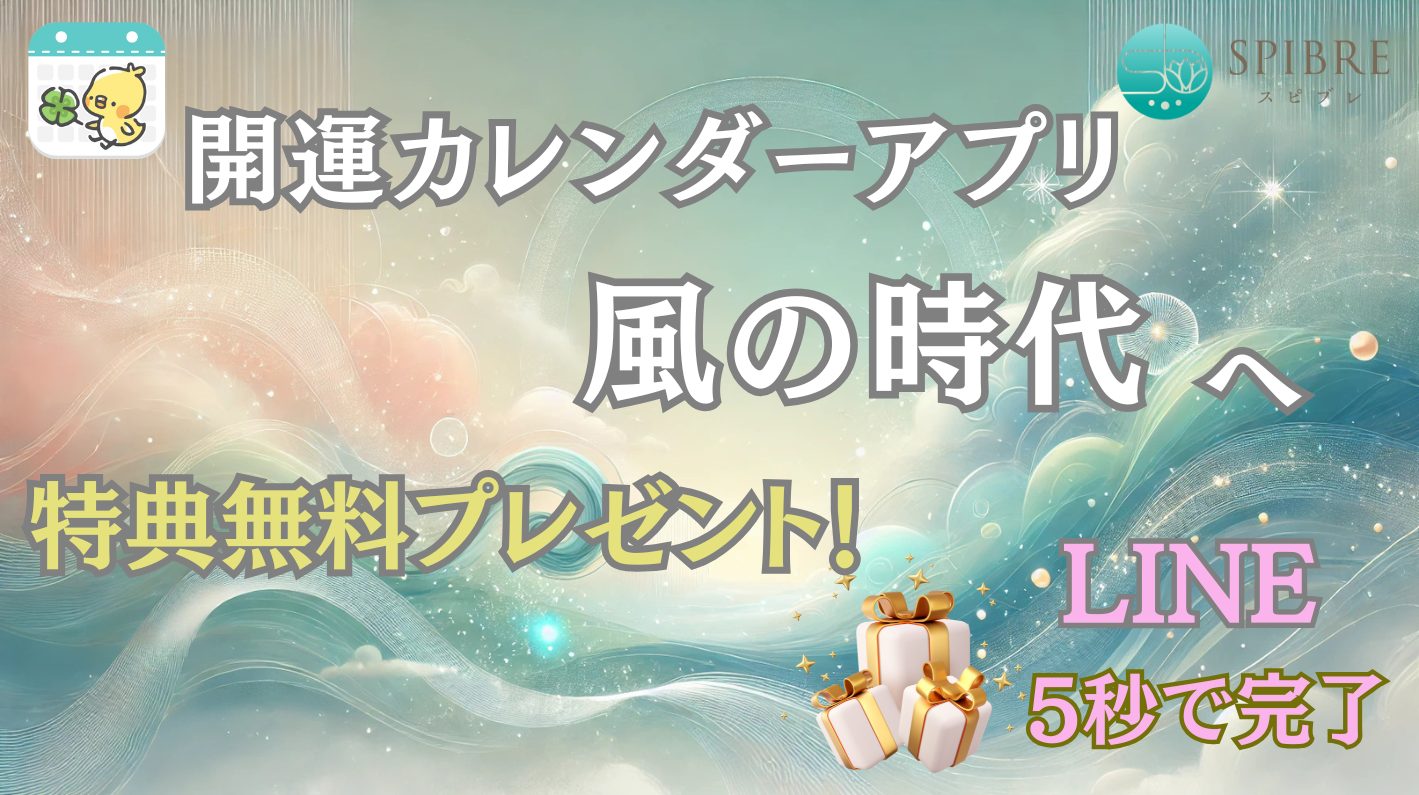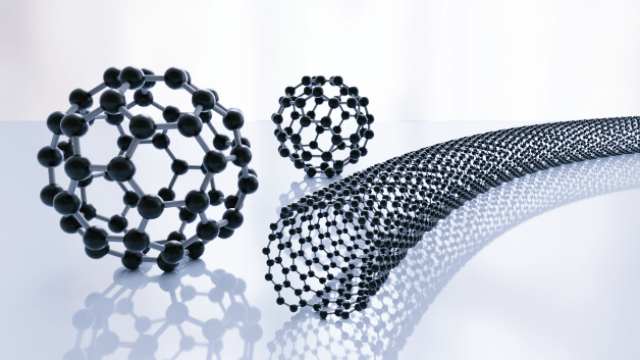私たちが日々何気なく使っている日本語の中には、仏様の教えが込められた、仏教用語に由来している言葉がたくさん存在しているのをご存じでしょうか?
たとえば「堂々巡り」など、同じところを繰り返し回っていて空回りしていることを表す言葉も、実は神仏に祈願するために、お堂の周りを巡り歩くという仏教用語から来ているのです。
ではいつも使っている言葉で、仏教に由来するものにはどのような言葉があり、どのようなスピリチュアル的な意味があるのでしょうか?
油断

『油断』という言葉は、日常茶飯事に使っている言葉ですが、これも仏教に由来する言葉なのは驚きです。
気を緩めずに注意を怠るなという意味なのですが、かつては神様や仏様に捧げる灯火は絶やしてはならず、油切れを起こさぬよう、油が断たないように大切にするという教えが仏教にはありました。
そこから生まれた言葉が「油断」であるという説があります。
このほかにもインドには次のようなお話があります。
インドのある王様が、自分の家来に油の入った鉢をひとつ持たせました。
そしてその家来がいかなる行動を取るときにも、一滴でもその油をこぼすようなことがあれば、その家来を殺すと告げたのです。
そのうえ、なんと抜いた刀を持った別の家来を、その油の鉢を持った家来のうしろから歩かせたのです。
油の鉢を持った家来は、細心の注意を払ってその鉢を持ち歩き、ついには一滴も油をこぼさなかったのです。
このお話のように、細心の注意を払うことで油を断たなかったことから、かつてのインドでは油が大変貴重で、不注意により油をこぼしたり失ったりしないようにという意味で「油断」という言葉が生まれたのです。
どっこいしょ

立ち上がるときや、重いものを持ち上げるときによく『どっこいしょ』と自然に使っています。
自分でも知らぬうちに「どっこいしょ」と発しているときは、ある意味気合を入れたり、さあこれからことを起こすぞ!という励ましにもなっていますね。
実はこれも、正真正銘の仏教語が語源となっています。
かつて山岳修行をしていた行者たちが「六根清浄(ろっこんしょうじょう)」と、唱えながら山を歩いていました。
六根清浄とは、人間が備え持つ6つの知覚:目(視覚)、耳(聴覚)、鼻(嗅覚)、舌(味覚)、身(触覚)の五感に心を加え、これらが穢れたときに清らかにすることを意味します。
そしてこの「六根清浄」という掛け声が、山登りで疲れてくると、だんだんと「どっこいしょ」となまってしまったということなのです。
仏頂面

何か気に食わないことがあったりして、ぶすっとした顔をしている人のことを「あの人は、『仏頂面』をしている」なんて言いますよね。
この仏頂面も仏教に由来する言葉なのです。
仏頂面の仏頂は、実は仏頂尊という仏様のことであるとされています。
仏頂尊は、仏様の頭の上に宿っている功徳から生まれた仏様のことなのです。
この仏頂尊のお顔は、威厳に満ち知的ではあるものの、ぶすっとした不愛想で不機嫌な表情なので、このようなぶすっとしている人のことを「仏頂面」と呼ぶようになったのです。
我々人間にとって、仏頂面をしていると、愛想が悪いだの、陰気だのと悪い印象を与えてしまいますが、実は仏様としてはこの仏頂面は吉相のひとつとされています。
一蓮托生

『一蓮托生』とは、一般的に良いことも悪いことも、いつでも運命をともにするというようなときに用いられる言葉です。
この語源は、死後に極楽浄土に行くと、菩薩様と同じ蓮の上に生まれるとする、浄土教の考えに由来しています。
人は亡くなると、その性別、そして生前の身分に関係なく、極楽浄土に行くことができれば、誰もが神聖な蓮の花とともに生まれ変われるという仏教の教えなのです。
どんな時でも、仲間を見捨てずに最後まで一緒であるという「一蓮托生」は、夫婦や友人との絆を表す言葉でもあります。
金輪際

『金輪際』という言葉は、何か悪いことをしたようなときに「もう金輪際悪いことはいたしません!」などというふうに使われることがあります。
この金輪際は、絶対にとか強い意志を感じる否定的な言葉ですが、仏教の世界観のひとつから来ている仏教用語なのです。
仏教において「須弥山(しゅみせん)-仏教の世界観で宇宙の中心にそびえる聖なる山のこと」という世界観があります。
それによると大地は虚空(こくう=空中)に浮かぶ、風輪・水輪・金輪という3つの輪が積み重なった上にのっているとされているのです。
その虚空の最上層である金輪と、その下にある水輪との際は、金輪の際なので「金輪際」と呼ばれています。
その金輪際は、地上に住んでいる人間にとっては、決して行くことのできない「果ての場所」にあたることから、物事の極限や最後を表す言葉となったのです。
おかげ

「●●のおかげ」とか「おかげさまで」などと用いるこの「おかげ」という言葉も、実は仏教から来ているのです。
「おかげ」とか「おかげさまで」は、相手に対する感謝を表す言葉として用いられていますが、もともと「おかげ」とは、神仏の助けやご加護のことを意味しています。
したがって「おかげ」とは、神様や仏様のおかげですというような意味に起因しているのです。
この「おかげ」に関する仏教のお話がインドに残っています。
インドの都市である王舎城(おうしゃじょう)に、シンガーラカという男性が住んでいました。
彼の父が亡くなりその遺言に従い、彼は毎朝、東西南北と上下の六方向に礼拝をしていましたが、なぜそれをしなくてはいけないのか、なんの意味があるのかは、まったく理解していませんでした。
するとお釈迦様は、彼にこう言いました。
「東方を拝むときには、生み育ててくださった父母に感謝し、南方を拝むときには、導いてくださった師に感謝し、西方には妻や子、北方には友人に、上方は沙門に、下方は目下の人々のあなたに対するご苦労に感謝しなさい。これが六方向を礼拝するという意味なのです」
つまりお互いにそれぞれが関係しあい、いろいろな人の力、おかげ、恵を受けて生きているのであるから、それらすべてに感謝をしなさいということなのです。
なんとなく使っている「おかげ」という言葉も、実は意味が深いですね。
まとめ
普段からよく使っている言葉の多くに、仏教にまつわるお話や起源があることには、今までなかなか気がつかずにいた人も多いことでしょう。思っていた以上に深い意味があったり、何等かの教えが盛り込まれていたりと、仏教ならではのお話も興味深いものが多くあるのです。