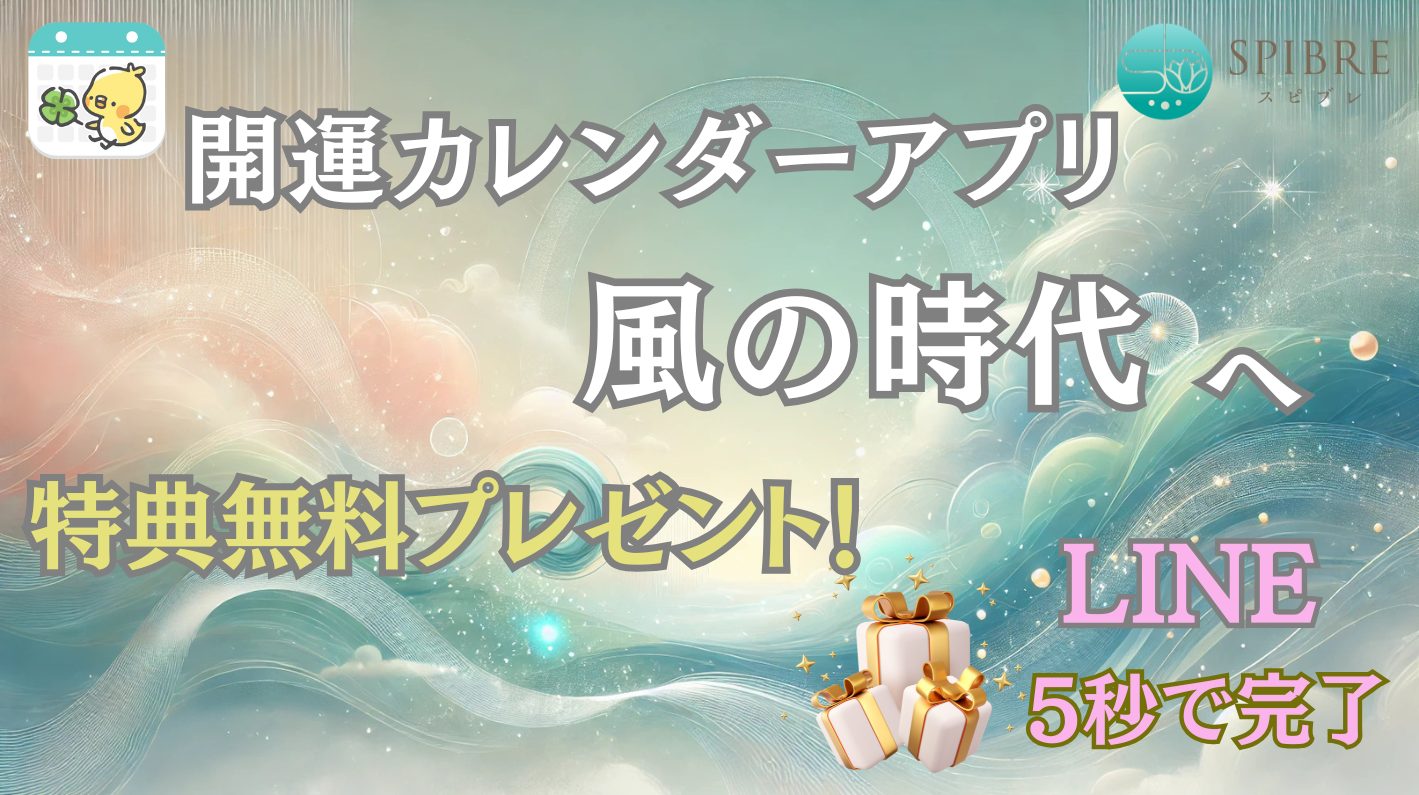天照大神といえば思いだすのが、天岩戸の神隠れのお話しではないでしょうか。
日本における最高位の神様でありながら、男性神であったとか女性神であったとか、あるいはその呼び名もいろいろと存在するようで、謎も多い神様のようです。
そんな天照大神の本当のお姿とは、どのようなものだったのでしょうか?
天照大神とは

天照大神は「あまてらすおおみかみ」、あるいは「てんしょうだいじん」と読み、日本神話にも登場する神様です。
皇室、および日本国民の神として、文字通り天を照らす太陽の神であると同時に、神御衣を織らせ、神田の稲を作り、天皇が即位の礼の後に初めて行う新嘗祭である大嘗祭も司る神様とされています。
天照大神は、月読命(つくよみのみこと)と須左之男命(すさのおのみこと)と共に、イザナギ命とイザナミ命の3人の子供のひとりとして生まれ、高天原(天上の国)を治めていましたが、ある日訪ねてきた弟の須左之男命が、乱暴をふるい天照大神のもとで働いていた機織り娘を事故死させてしまったことから、機嫌を損ねた天照大神は、天岩戸に引きこもってしまったのでした。
太陽神に隠れられて、世の中は闇となり、困った神々が岩戸の前で楽しく踊り始めたところ、岩戸を少しだけ開けて何事か見ようとした天照大神を、みんなで引き出し戻れないようにしたことで、この世に太陽が戻ったとされています。
天照大神、天照皇大神、天照御大神の違いは?
天照大神には、ほかにもいろいろな呼び方が存在しています。
古事記では天照大御神、日本書紀では天照大神、そして伊勢神宮においては天照皇大神(あまてらすすめおおかみ)と呼んでいます。
また伊勢神宮において、神職が神前で名を唱えるときは、天照坐皇大御神(あまてらしますすめおおみかみ)と言われています。
このほかにも大日霊(おおひるめ)、大日女(おおひめ)、大日女尊(おおひるめのみこ)など、神社によっても様々な呼び名が存在しています。
どうやらそれぞれの時代によっても、神社や宗教の宗派の違いによっても、名前がいろいろと存在するようです。
天照大神のご利益

太陽神であり、天皇の祖神であり、そして日本の最高神である天照大神は、国に平和と豊かさを与える神として、伊勢神宮の祭神でもあります。
そんな天照大神のご利益は、国土安泰、開運、勝運、福徳とされています。
また伊勢神宮においては、外宮からお参りをし、その次に内宮、別宮とお参りすればさらなるご利益を得られるとされています。
このほか「あまてらすおおみかみ」と声に出して10度唱えるだけでも、マントラと同じく、邪気を払う効果があるとされています。
天照大神の祀り方

天照大神を自宅でお祀りするには、まず神棚を用意します。
神棚は、清潔で拝みやすい場所、また神棚を置いた下は潜り抜けられない場所である必要があります。
そして神棚は南か東に向けて飾るようにします。神棚に伊勢神宮でいただける「天照皇大神宮」と書かれたお札を中央に祀ります。
そして神棚に榊や蝋燭、鏡などの神具を置きます。
神棚にお参りするときは、まず手を洗い、口をすすいでから米、水、塩をお供えし、お酒や海の幸、山の幸もお供えします。これらのお供えが終わってから、神社にお参りするときと同じく、二拝二拍手一拝をして、朝夕に拝むとよいでしょう。
神棚が置けない場合は、清潔な戸棚の上など、失礼のない高い場所に、白い布を敷いた上に南か東を向けてお札を置いてください。
神社によってはお札立てを販売しているので、それを利用するのもよいでしょう。氏神様や鎮守様のお札も飾るときは、天照大神が中央、向かって右が氏神、左が鎮守のお札となります。
天照大神のゆかりの地
全国には天照大神をお祀りする神明神社と呼ばれる神社が多数存在しています。
ぜひ一度、天照大神をお祀りした近くの神社に足を運んで、ご利益を授かってみてはいかがでしょうか。
伊勢神宮

その総本社は、伊勢神宮(三重県伊勢市宇治館町1)で、三種の神器のうちのひとつである八咫鏡(やたのかがみ)をご神体として安置しています。
天岩戸神社

宮崎県の天岩戸神社(宮崎県西臼杵郡高千穂町)は、天照がお隠れになったという天岩戸をご神体として天照大神をお祀りしています。
廣田神社

兵庫県にある廣田神社(兵庫県西宮市大社兆町7番7号)は、日本書紀にも記載がある神社で天照大神の荒御魂をお祀りしてあります。
宗像大社

福岡県の宗像大社(福岡県宗像市田島2331)では、天照大神の息吹よりうまれた3人の女神をお祀りしています。
まとめ
いかがだったでしょうか?
日本神話に登場する天照大神の名前は、誰もが知ってはいるようでも、詳細についてはそれほど知られていなかったかもしれませんね。
日本の神様の最高位に存在される天照大神のゆかりの地に、一生のうちに一度は拝みに行きたいものです。
▶︎日本全国都道府県の神聖なパワースポットまとめ一覧ページはこちら