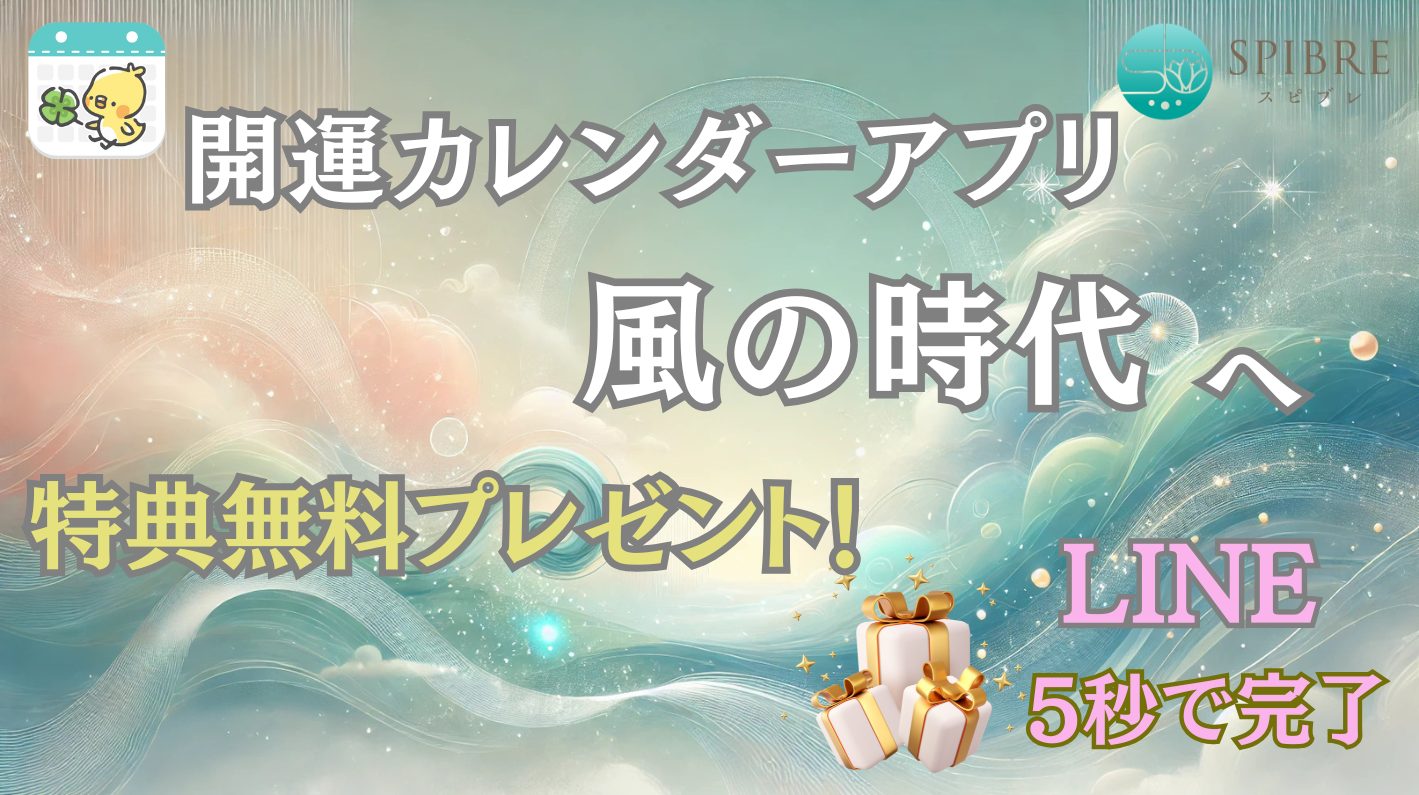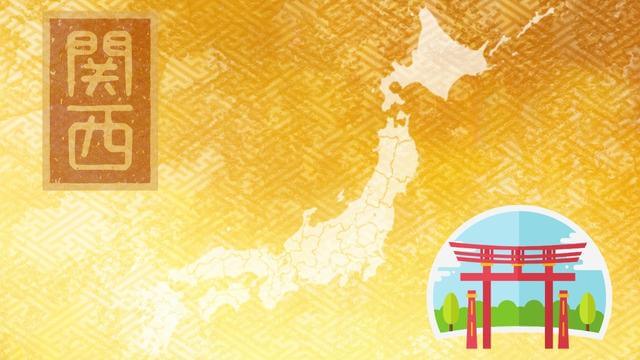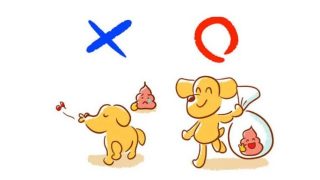大阪市の中心地にある「難波八阪神社(なんばやさかじんじゃ)」は、地元の人たちのみならず、国内外の観光客にも注目を浴びている、パワースポットです。
なんとその神社には、驚くほどインパクトのある『獅子殿』と呼ばれる、巨大な獅子頭の社殿が鎮座しているのです。
ある意味大阪らしい、派手で強烈なイメージの社殿を持つこの「難波八阪神社」ですが、その歴史やご利益などには、どのようなものがあるのでしょうか?
「難波八阪神社」の起源

「難波八阪神社」は、大阪市の中心にある繁華街『なんば』からは、少しはずれた場所にあります。
その創建については、大阪大空襲で資料が焼失したため、さだかではありませんが、仁徳天皇の時代には存在しており、「難波下の宮」と呼ばれ、この地一帯の産土の神であったのです。
この地区に疫病が流行り、それを治めるために神仏習合の神である牛頭天王(ごずてんのう)が現れ、この神様をお祀りしたのが「難波八阪神社」の始まりなのです。
1069年~1073年の後三条天皇の頃には、『祇園牛頭天王(ぎおんごずてんのう)』をお祀りする神社として定着し、世間に広く知られるようになりました。
この時代でも神仏習合が続き、境内には神社のほかに神宮寺も存在していました。
明治維新後に神仏分離となったため、寺院が廃絶となり1872年には郷社(神社の社格のひとつ)となりました。
大阪の大空襲で社殿が全焼し、現在ある本殿は1974年に再建されたものです。
境内の西側には『獅子殿』と呼ばれる大きな獅子頭の社殿があり、こちらも1974年に完成しました。
この神社の総本山は、京都祇園の「八坂神社」ですが、この神社は「八阪神社」であり、坂の字が京都の総本山とは違っています。
これは大阪の「阪」にちなんで、このように付けられています。
またこの神社のユニークなポイントとしては、大日本帝国海軍の戦艦「陸奥(むつ)」の、大砲の先端に設置されていた蓋が展示されています。
戦艦陸奥は、太平洋戦争の終戦直前に、戦艦に積んでいた火薬が爆発して沈んでしまいました。
そのときに、この戦艦と共に亡くなられた1121名の将校と兵士の皆さんの魂の慰霊と、平和を祈ってこの蓋が安置されているのです。
「難波八阪神社」の獅子頭社殿

圧倒されるような巨大な獅子頭の『獅子殿』は、高さが12メートル、幅11メートル、奥行き10メートルもあります。
この獅子頭が創建された理由は、この地域が昔から獅子舞が盛んであったこともあり、また獅子頭は魔除けにもなるので、大阪の新しいシンボルとなるように、この巨大な獅子頭の社殿が作られたのです。
『獅子殿』の口の中へ入って行くと、入口には24本の黄金(真鍮)の歯が輝いています。
そして口の内部といえば、見事な神殿になっていて、天井には手彫りで仕上げられた素晴らしい鳳凰模様があしらわれているのです。
この『獅子殿』の内部には、素盞嗚尊(すさのをのみこと)のふたつある霊魂のうち、荒々しい性格の荒魂(あらみたま)と、加賀獅子(かがじし)という獅子頭が、唐櫃(からひつ)という箱の上に一対安置されています。
また『獅子殿』の周囲には、大阪に本社のある有名な会社の名盤が、多く彫られています。
これらの会社は、この「難波八阪神社」を産土の神としてお参りを欠かさなかったところ、業績がアップしたことから、お礼と感謝の気持ちを込めて神社に寄付をされたのだそうです。
「難波八阪神社」の獅子頭社殿のご利益とは

「難波八阪神社」は、地元の会社がその発展を願ってお参りし、実際に業績がアップされているのです。
勝負運にもご利益があるということで、スポーツで試合のある人たちや、芸能関係の人たちがよくお参りに行かれます。
また獅子頭であることから、その口が邪気を飲み込むとされ、学業に関する願い事、試験合格、就職内定などにもご利益があります。
「難波八阪神社」御祭神とご利益

「難波八阪神社」の御祭神は、厄除け、商売繁盛などにご利益のある『素戔嗚尊(すさのおのみこと)』が中心です。
実はこの神社の創建当時に祀られていた「祇園牛頭天王」は『素戔嗚尊』のことであるとされています。
また縁結びや安産などにご利益のある『奇稲田姫命(くしいなだひめのみこと)』、そして『素戔嗚尊』と『奇稲田姫命』の間に生まれた8人の皇子:天忍穂耳尊(あめのおしほみみのみこと)、天穂日命(あめのほひのみこと)、天津日子根命(あまつひこねのみこと)、活津日子根命(いくつひこねのみこと)、熊野久須毘命(くまぬくすびのみこと)、多紀理毘売命(たぎりびめのみこと)、多岐津比売命(たぎつひめのみこと)、狭依毘売命(さよりびめのみこと)が祀られています。
ご利益:厄除け、商売繁盛、縁結び、安産、疫病退散、入試合格、交通安全、家内安全
「難波八阪神社」の神事や祭事
「難波八阪神社」では、毎年1月の第3日曜日に、大阪市指定無形民俗文化財の指定となっている「綱引神事(つなひきしんじ)」が執り行われます。
これは「素盞嗚尊」が、かつて人々を苦しめていた八岐大蛇(やまたのおろち)を退治し、多くの人を苦しみから救ったことが由来で、江戸時代より毎年行われています。
祭りでは大蛇に見立てて太く編まれた縄を、その年の恵方に向かって引き合います。
その後その縄は神殿にお祀りされ、家内安全、商売繁盛を願い、疫病災厄のお祓いを行います。
このほか、7月には道頓堀川で行われる「船渡御(ふなとぎょ)」があり、江戸時代は大阪で最も有名な、天神祭りと並んで行われていた祭事です。
この行事は一旦途絶えていたものの、2001年に230年ぶりに復活し、約20隻の渡御船が道頓堀川を行き交います。
毎年7月13日が宵宮で、翌14日が本宮となります。
●難波八阪神社:大阪府大阪市浪速区元町2-9-19
●アクセス:大阪メトロ「なんば駅」より徒歩6分
まとめ
大阪市内の街中にある「難波八阪神社」は、非常にインパクトのある「獅子殿」があることで有名です。国内外からの観光客にもパワースポットとして人気があるほか、地元の人々や会社からも氏神様として古くから親しまれてきた神社なのです。
▶︎暦の流れに沿って生きると自然に開運できる*幸運を呼ぶポイントはこちら